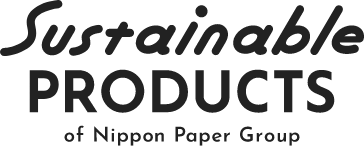畜産王国みやざき!
〜元気森森®で日本を元気に!!〜
食料安全保障とフードテックの最前線を探る宮崎発の情報番組です。毎週、自治体、企業、生産者など多彩なゲストをお招きし、畜産業界の最新情報や専門知識を共有します。
TALK THEME
トークテーマ
畜産業に携わる方々や、これから畜産を始めたい方、そしてフードテックに関心を持つリスナーに向けて、さまざまな情報をお届けします。
-
ゲストトーク
毎回畜産や食に関する知見者にお越しいただき、幅広くお話を伺います。
-
元気森森®コーナー
日本製紙社員とゲストによるクロストークです。元気森森®についてさまざまな角度から掘り下げます。
-
王国のホッとタイム
ラジオではお伝えしきれなかった出演者のスペシャルトークをYouTubeで限定公開します
PERSONALITY
パーソナリティ
-

大野 泰敬
株式会社スペックホルダー代表取締役
農林水産省政策研究所客員研究員 -

奥山 真帆
エフエム宮崎アナウンサー
番組への質問・メッセージはこちらからお送りください。
morimori@joyfm.co.jpCONTENTS
コンテンツ
YouTube「王国のホッとタイム」は「ちくほっと」でご覧いただけます
-
2025.09.28
輸出を増やし畜産業に明るい未来を
アナウンサーからの華麗なる転身今回のゲストはNIKUJILLE 代表取締役社長 有田ジェームスさんです。三好ジェームスさんとしてテレビで活躍されていたことをご存じの方もおられると思います。アナウンサーから牛の世界に入ったジェームスさんは牛肉を輸出するためにNIKUJILLEを設立されました。2021年に設立し、たった4年で世界29か国に輸出するまでになりました。
急成長のポイントは「(熱い)気持ち!」そして「どこで、だれが、どのように育てたか」を伝えるブランディングで商品の差別化を図り、それをしっかり伝えること。日本の職人気質で育てられた牛、こだわりの牛。必ず差別化できるポイントがあるはずです。それらを可視化することが海外に出ていく第一歩だそうです。
ジェームスさんは宮崎県有田牧畜産業のご親族です。でも有田牧畜の牛肉だけ輸出しているわけではありません。五年後、十年後に牛飼いになりたいと若者に思われる業界にするために、日本の牛肉を世界に輸出する仕組みを作りたいと世界中を飛び回っています。
ジェームスさんも海外のニーズがA5ランク主流からA4、A3に移るときがくる、と言います。世界の潮流が変わりつつあるのかもしれません。日本の畜産を発展させるため、日本からの輸出を増やしていくために関係各社がそれぞれの力を持ち寄ってパワーを出すことが必要だと、ジェームスさんは輸出に特化した新たな仕組みを構築中!生産者にとって輸出しやすく、生産者が儲かる仕組み作りにはパーソナリティ大野が興味津々。
「王国のホッとタイム」でも熱いトークが続いています。畜産業を発展させるため、NIKUJILLEは今日も世界を駆け巡ります‼ -
2025.09.21
おいしさ最優先!生乳の味を伝えたい
川南町のブランドを守る乳業メーカー今回のゲストはアリマン乳業有限会社代表取締役ミルクアドバイザー三浦崇さんです。アリマン乳業の牛乳といえば「トロントロン牛乳」、低温殺菌で生乳のおいしさがわかる牛乳です。牛乳のパッケージには児湯郡を代表するイラストが描かれています。同社のもう一つの代表商品である「とろんとろんヨーグルト」もおいしさ最優先で自然発酵にこだわっているそうです。
一度会社を辞め、経営を建て直すために戻ってきた三浦さん。決算書をみてがく然としたものの、先代からのブランド「トロントロン牛乳」がしっかりあったので、それを軸に事業を復活させました。
今は乳業メーカーとして酪農家と消費者をつなげる活動もしているそうです。これからの酪農経営は「今までの価格を守る右手」と「付加価値をつける左手」のバランスが大切とのこと。納得の経営論をぜひお聞きください。
アフタートーク番組「王国のホッとタイム」では、まずおいしそうな商品を試食!そこで全員が注目したのはお薬を飲むためのアイスクリーム!なんと高校生が開発した商品なのだそうです。おいしい!ふつうに食べておいしいアイスでした!
次は「恋するカフェオレ」。コーヒーの苦みと渋みを感じながら生乳の風味と見事にマッチ!絶対おすすめです! -
2025.09.14
人の命の源を支え、食卓を豊かにする
飼料生産から牛肉輸出まで一挙に手掛け年商600億本日のゲストは株式会社カミチクホールディングス代表取締役社長 上村昌志さんです。1985年創業のカミチクはグループの年商600億!世界を回って30年前から食料危機が来ると感じ、食料残渣を使ったエサ作りを始めました。その後は加工、外食まで一気に経営を広げていきます。大切なのは「出口戦略」と、今ではワタミと合弁会社「ワタミカミチク」を設立し、さらに販路を拡大しています。
そして、世界を見てきた上村さんは「A5ばかり注目されるがこれからはA4、A3になってくるのでは」と変化の予兆を感じているそうです。
積極的な経営の原点は「畜産は人の命の源を支え、食卓を豊かにする素晴らしい仕事だ。ただ、自分で値段が決められないのがくやしい」という父親の代からの思い。上村さんは、畜産業の発展のため、自分の農場以外の販売でも協力し、一緒に農業畜産を盛り上げていきたい、と熱く語ります。「王国のホッとタイム」では、カミチクホールディングスを一代で築き上げた上村さんの経歴について伺いました。年商600億の大手企業になったカミチクですが、上村さんは大学中退後、畜産や卸売業を経験され、26歳でカミチクを創業、もともとは小さな会社だったそうです。「誠実に」「謙虚に」事業にとりくみ、自分の肉が高く売れないという農家のくやしさを忘れず、ここまで大きくなりました。
上村さんは農家さんの経営相談を受けることも多いそうです。その時にチェックする5つのポイントをご紹介。①しっかりした元牛がいるか、②よいエサが作れているか、③飼育管理技術、④安定的な販売先がいるか。⑤はぜひこのYouTubeをご覧ください。 -
2025.09.07
「元気森森®で育った牛 実感試食フェア」開催報告
今回は8月27日に開催された「元気森森®で育った牛 実感試食フェア」のようすをお伝えします。
今までこの番組を通して、木から生まれた牛のエサ「元気森森®」について紹介してきました。繁殖成績改善、乳成績向上、枝肉重量増などの機能はすでに採用された農家さんから報告いただいています。実際、お肉の味が変わるのか?どう変わるのか?!試食会加者の声もお届けします。
今回の肥育試験を実証してくださった鏡山牧場代表取締役八崎秀則さんから試験結果もお話しいただきました。大幅な飼料設計の変更なしで肉質の改善ができ、使用環境も良くなったと太鼓判を押されます。
それから、八崎さんお勧めの「塩」もご紹介いただきました。「肉にはこれ!」なんだそうですよ。お楽しみに。 -
2025.08.31
エコフィードで食の循環、センサーで子牛の命を守る
二刀流イノベーションの旗手今回のゲストは、株式会社カスケディア・トレーディング経営企画室室長 児島祥浩さんと広報 稲村恵玖実さんです。同社は牧草、飼料、機械、システムまで、畜産に必要なあらゆるものを販売し、「畜産農家のお役に立ちたい」という熱い理念を掲げています。コロナ禍や為替の影響で牧草の価格が厳しくなる中、牧草以外の分野で、農家さんが本当に必要とするものを積極的に提案してきました。特に注目したいのが「エコフィード」への取り組みです。青森と熊本に工場を設立し、事業を推進しています。青森ではリンゴジュースの搾りかす、熊本ではコーヒーチェーン店のコーヒー粕などを飼料として活用。リンゴの搾り粕は、繊維質が豊富で香りも良く、牛が喜んで食べる「美味しいふりかけ」のような存在なのだそうです。しかし、食品残渣の飼料化には「水分」という大きな課題があります。保存性を高めるには乾燥が必要ですが、その設備を持つ企業は少ないのが現状です。そこで同社は、水分を大幅に減らす「圧縮」技術に注目し、現在、大手企業と共同で新しい機械の開発を進めています。このエコフィードの取り組みは、廃棄物を飼料、そして美味しいお肉に変え、ブランド化を目指すという、まさに「食の循環」を生み出す素晴らしい展開となっています。さらに、同社は「子牛の命」を守る画期的なシステムも手掛けています。鹿児島県の平松畜産では、1700頭の子牛に24時間センサーを取り付け、行動を監視。日本では約400万頭の牛が生まれている中で生後4か月まで年間8万頭もの子牛が命を落としているという現状に対し、このシステムは子牛の死亡率を劇的に改善し、畜産農家の大きな悩みを解決しています。飼料コストの削減だけでなく、社会課題の解決にも貢献し、地域全体を笑顔にする事業を目指す同社の挑戦に、これからも目が離せません!
アフタートークでは、異業種から畜産業界へ転身した3名のメンバーが、その挑戦と学び、そして情報発信への熱い想いを語りました。実家が酪農を営む稲村さん、食品メーカー出身の小島さん、紙分野から社内異動をした都合さん。彼らは「F1」「交雑種」といった業界用語や畜産業界の複雑さに戸惑いながらも、ベテラン農家の方々から直接学びを深め、日々奮闘しています。この専門性の高さを解消するため、稲村さんたちは、社内向けには牛の一生を漫画で解説したニュースレターを作成。社外向けにはSNSを積極的に活用し、Instagramでの子牛の写真投稿で大きな反響を得たり、YouTubeで農家インタビュー「MowTube」やショート動画を制作したりターゲットに合わせた情報発信を工夫しています。農家の方々もSNSを積極的に見ている現状を踏まえ、彼らの情熱と工夫に満ちた情報発信の裏側が垣間見えるアフタートークとなりました。ぜひ、お聴きください。