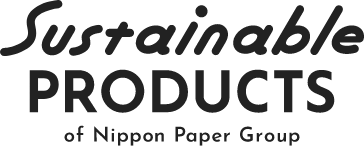木から生まれた牛のエサ「元気森森®」
元気森森®のさらなる発展のために日々探求を続ける
基盤技術研究所木質素材研究室Ⅰ
根岸弘行
東京都北区王子にある基盤技術研究所の研究棟は2000年に建設され、基盤技術研究所、パッケージ研究所、知的財産部が入居しています。木から生まれた牛のエサ「元気森森®」はここから生まれました。
基盤技術研究所(東京都)
パルプの製造現場を知る研究者として
入社後は紙の原料であるパルプの製造現場の基礎を深く理解したいという思いから、釧路工場(現:釧路事業所)の製造部門で経験を積みました。その後、研究所へ異動。紙の需要が減少する現代において、紙に代わる「第二の矢」となる新たな事業の創出を目指し、日々試行錯誤を重ねています。元気森森®の担当としては製品の付加価値向上や、給与データ解析による新たな給与効果の立証などに取り組んでいます。特許による他社参入の排除、パルプの特性を活かした類似品との差別化、そして更なる給与効果の拡充を常に意識しています。
ゆっくり分解が鍵!元気森森®が牛の消化と成長をサポートするメカニズム
牛には4つの胃がありますが、その中でも特に重要な役割を果たすのが「第一胃(ルーメン)」です。ルーメンの中は、人間の胃とは異なり中性で、多種多様な微生物が生息する特別な環境です。牛が草の主成分であるセルロースを分解できるのは、このルーメン内微生物のおかげであり、最終的に酢酸やプロピオン酸等の短鎖脂肪酸まで分解されます。私たちが開発した「元気森森®」の主成分であるセルロースは、ルーメン内での分解速度が非常にゆっくりです。この「ゆっくりとした分解」のおかげで、分解物によるルーメン内の急激なpH変動が起こりにくくなります。そのため、ルーメンへの負荷が少なく、牛の消化能力を好調に維持し、健康維持に貢献できるのです。
さらに、元気森森®を与えることで、繊維分解微生物が増えることも確認されています。これにより消化性がさらに向上し、牛の健康に良い影響を与えると考えられます。生成された短鎖脂肪酸は、牛の日々のエネルギー源として代謝されるだけでなく、微生物がタンパク質を分解するエネルギーとしても利用されます。結果として、タンパク質の利用効率が向上し、牛の健やかな成長にもつながるのです。

元気森森®のネーミングとロゴに込められた想い
元気森森®のネーミングとロゴは、私が担当になる前から決まっていました。当時の担当者から聞いた話によると、現場で受け入れてもらえる親しみやすい名前を、という思いから、この飼料を食べた牛が元気いっぱいになるようにと願いを込めて「元気森森®」と名付けられたそうです。また、木から製造していることをアピールするため、「森」の漢字が使われています。ロゴは、当時の新素材営業本部パッケージング・コミュニケーションセンター(現バイオマスマテリアル事業推進本部バイオマスマテリアル・コミュニケーションセンター)に考案してもらいました。元気(Genki)の「G」と森のモチーフを掛け合わせたデザインで、親しみやすく、見る人に活力を与えるような仕上がりで大変気に入っています。

試行錯誤とひらめきが拓く元気森森®の未来
研究開発は常に未来を見据え、前向きな探求を続けるため、非常にやりがいのある仕事です。あらゆる仮説を立て、それを実行し、結果が出た時に大きな喜びを感じます。そのため、日頃からさまざまな文献を読み込み、元気森森®のさらなる発展に繋がる開発は何か、模索探求しています。また、展示会や出張先での新たな出会いが、思わぬ形でプロジェクトが広がることも多く、そうしたご縁にも深く感謝しています。皆さんに良い情報をお届けできるよう、これからも尽力していきます。
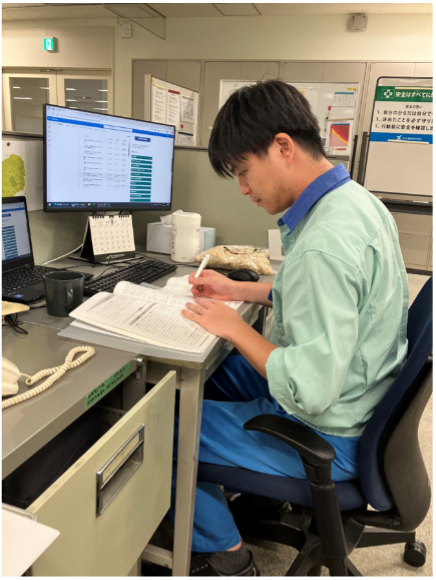
取材日:2025年8月21日
企画:バイオマスマテリアル・コミュニケーションセンター
写真:日本製紙株式会社