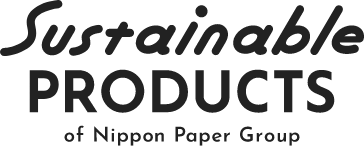元気森森®スペシャル対談
株式会社スペックホルダー 大野泰敬
日本製紙株式会社バイオマスマテリアル販売推進部 久保直也
「サプライチェーン有事に日本の飼料を支えるのは元気森森®しかない!」と言う元気森森®サポーターの大野さんと、「牛にも農家さんにも喜んでもらえる元気森森®は素晴らしい飼料!」と胸を張る元気森森®営業担当の久保さん。お二人が元気森森®について熱く語ります。

木から生まれた牛のエサ「元気森森®」の特長
大野:木から生まれた牛のエサ「元気森森®」。木がエサになるってすごいですね。
久保:そうですよね、皆さんそう言われます。
元気森森®は木から牛が消化できないリグニンを除去し、高純度のセルロースを取り出しており、ほぼ全てを牛が栄養として吸収、消化できる飼料です。一番の特徴は、濃厚飼料のエネルギー摂取効率の良さと粗飼料の緩やかな消化吸収との両方を持っているところです。

大野:元気森森®は高エネルギーでありながら緩やかな消化という2つの利点があるのですね。データを見ると、消化率とTDN*がとても高いですね。
*TDN:可消化養分総量。消化・吸収できる栄養分の総量。
久保:木は主にリグニン、セルロース、ヘミセルロースという3種類の成分から構成されています。セルロースは牧草にも含まれている成分ですが、元気森森®は牛が消化できないリグニンを取り除いているため、粗繊維の割合が乾物換算で82.3%と高く、消化率は約97%です。ほとんど消化できるので、結果としてTDNが95.6%と、濃厚飼料並みとなっています。
大野:元気森森®は牛の胃の中で活動する微生物にどのような影響を与えていますか?
久保:セルロースはそのままでは栄養として吸収されません。ルーメン*内にいる微生物がセルロースを分解してエネルギーになります。セルロースの分解速度は、TDNが同程度のトウモロコシの子実などの飼料と比べると遅く、ルーメンアシドーシス*の原因となる揮発性脂肪酸(VFA)の出方も緩やかです。VFAの出方が早いとpHが下がってしまい、微生物の数や活動が下がったり悪くなったりするのですが、そのリスクが低い成分と言えます。したがって微生物には良い影響を与えていると思います。
*ルーメン、ルーメンアシドーシス:ルーメン(牛の第一胃)のpHが下がる状態

大野:元気森森®がこの製品形状なのには、何か理由があるのですか?
久保:既存のパルプ製造設備を応用して作り出したものなので、「この形状でできあがってくる」というのが正直なところです。お客さまの中には、柔らかいセンイだから子牛の腹づくりのトレーニングにちょうどいい、と言って下さる方もいます。一方で反すう刺激の面から物理性がちょっと足りないと思われる方には、対象牛によりますが、単体で使うより、粗飼料や反すう刺激のある飼料と併用していただくことをお勧めしています。
元気森森®が生まれた切実な理由

大野:なぜ日本製紙は元気森森®を作ったのですか?
久保:紙パルプ事業の販売数量が年々下がり、今後もその需要回復が見込めない中で、売上が期待できる紙以外の新事業を立ち上げることが課題の一つでした。研究部門の担当者が、牛にとって必要不可欠な牧草の主要栄養源がセルロースである点に着目したこときっかけに、木材パルプの養牛飼料用途について検討を開始しました。2015年に大学や研究機関と連携して、牛のエサとしての給与テストを始めました。
大野:いつから商品化のめどが立ってきたのですか?
久保:大学や研究機関での効果実証が2019年に終了し、実際の畜産現場での実証テストに向けて営業活動を開始しました。そして、2021年に採用第一号が生まれました。
大野:一般的に、「責任が重いから」といって、新規事業で食にまつわる事業を避ける企業が多いです。しかし元気森森®は、長い期間さまざまな研究機関と連携しデータを蓄積してその懸念を超える性能を明らかにして事業を進めたのですね。採用件数や販売数量は非公開ですか?
久保:そうなんです。すみません!(笑)。でも、ちょっとだけ雰囲気をお伝えしますね。ありがたいことに、2021年度の販売開始以降、2023年度にかけて、採用件数も販売数量も予想をはるかに超えるスピードで増加しています。認知度も期待も、日に日に高まっている感じがします。
大野:一度聞いたら忘れられない「元気森森®」という製品名にした理由を教えてください。

久保:当時研究部門で関わっていた10人程度のメンバー全員で案を出して、多数決で決まったそうです。お客さまからは親しみを込めて「もりもり君」や「元森(ゲンモリ)」などと呼ばれています(笑)。牛が元気になるので、ぴったりなネーミングだと自信を持っています。
新たなフィールドでの挑戦

大野:製紙会社の商材としてはユニークですよね。なぜ久保さんが担当になったのでしょうか?
久保:実は私、2020年3月までアイスホッケーの選手でした。「社会人」として再出発するにあたり「新しい商材を扱いたい」と希望し新素材を扱う部署に異動となり、元気森森®の担当になりました。最初は採用例が無い中、紹介に行ったお客さまからは「木を食べさせて本当に大丈夫なのか?」「誰も使わないよ」と言われたこともあります。一番に採用してくださった方は、元気森森®の説明をしたら「セルロース?あ、牧草の中の主成分ね、絶対悪いものじゃないね、乳脂肪に効きそう」とテスト給与を受けてくださいました。その後、私は「牛」や現場作業といった基礎的な部分から元気森森のさまざまな効果まで営業として必要なことすべてを教えてもらっています。今ではその方は私の師匠です(笑)。採用が増えるにつれ、さまざまな知見が生まれて、牛にとってもお客さまにとってもいいエサであることを確信しています。「お役に立てる商材」の担当であることは、とても幸せです。
元気森森®ユーザーの声
大野:実際に元気森森®を採用した農家の方からはどういった声が届いていますか?
久保:元気森森はエネルギー源としてはもちろん、使用方法によっては良好なルーメン環境維持が期待できますので、ほかの飼料の消化効率が良くなり、栄養の未利用分が減ることも期待できます。フンの状態が良くなる、エネルギーが充足する、健康になる、発情含め繁殖成績が向上する、乳成績が良くなるなど、給与対象の牛によって異なりますが、さまざまな効果が出ていると伺っています。

大野:体にとって良いものを摂取すれば、健康状態が良くなり、乳量の質も量も良くなる。さらに病気になるリスクも減るし、繁殖力も高まっていく、良い飼料ですね。
久保:そう実感いただけるために、今後どうやって知っていただき、ファンを増やし、採用を増やしていけるか、日々試行錯誤しています。
元気森森®をより広く知っていただくために
大野:昨今の飼料の価格高騰、外的要因による供給リスクが発生している中で元気森森®は国内で安定生産が可能で重要な飼料の一つだと思っています。実際、農家の方の飼料に対する考え方、感じ方は変わっていませんか?
久保:ウクライナへの軍事侵攻により、輸入飼料の価格が一気に上がり、安定して入ってこなくなりました。為替の影響も大きく受けています。その点、元気森森®は国内の工場で生産されるため安定品質・安定供給できる点も評価されています。一方で元気森森®の価格について厳しいお声をいただくこともあります。牛の調子が悪くなった時の手間やコストを減らすことができるなど、総合的な効果を実感し、評価いただければ嬉しいです。今後は元気森森®のメリットを数値化していきたいですね。
大野:数値化されることは良いですね。牛には体に良くて、安定的に生産されるので農家の方にも良い「元気森森®」ですが、今後はどうやって販路を拡大させていこうと考えていますか?
久保:具体的に2つあります。まず1つ目は元気森森®の認知度を上げることです。専門誌や新聞に広告を出したり、デジタル広告を出したり、展示会に出るなどして認知度を上げて、そこから問い合わせを増やしたいと考えています。
2つ目はパートナー企業の探索です。専門性があり地域密着で牧場と関係性を深めている企業に元気森森®の利点を認識してもらい、採用先の事例を紹介し具体的な使用方法や効果をイメージいただけるようにしていきたいですね。
新法成立で元気森森®が担う飼料安定供給のミッション
大野:2024年6月14日に「食料供給困難事態対策法」が可決成立しました。食料確保のほかに、飼料や肥料といった資材の確保が優先事項になっています。飼料は大量生産・安定生産でき、品質も一定である必要があります。飼料が輸入できない状況になったとして、国内で調達できる飼料をいろいろ探したのですが、代替えになりうるのは「元気森森®」だけだと思っています。
久保:そうなんですね!ありがとうございます。
輸入品が入ってこなくて、牛にエサを与えられなくなった時の大変さは直接お話を伺い、安定供給の重要性を認識しています。牛にとって良いエサであることはもちろん、使って良かったと思っていただける国産のエサですので、これからも自信をもって、お勧めしていきたいです。
大野:これからも日本の畜産飼料にとって重要な「元気森森®」を応援していきます。
企画:バイオマスマテリアル・コミュニケーションセンター
取材日:2024年5月31日
写真:株式会社スペックホルダーおよび日本製紙株式会社