
最初に標準寸法が決められたのは、昭和4年(1929年)に、当時の商工省が日本標準規格(JES)で「紙の仕上寸法」を発表したことに始まります。
それまでは、書籍や雑誌では日本古来の四六判、菊判が広く用いられ、しかも仕上寸法自体が統一されていませんでした。このときは、原紙の「標準寸法」としてA列、B列の2種類を定め、「仕上寸法」としてA列、B列ともに0番~12番までが決まりました。A4、B4というのはA列の4番、B列の4番という意味です。
規格統一にあたっては諸外国の例も調査し、A列にはドイツ規格のA列系統をそのままとり入れ、B列では日本独自の寸法を作ったのです。A列は0番を一平方メートル、B列は0番を1.5平方メートルとし、いずれも長辺と短辺の比を1対ルート2とした四角形で0番を半分に折ったものが1番となります。
製紙会社では洋紙を一定の寸法に切って供給していますが、特別なものを除いて代表寸法が決まっています。これを原紙寸法といいます。印刷後、四方を裁ち落として仕上げられるので原紙寸法は仕上げ寸法より一回り大きいサイズになっています。
日本工業規格での、印刷紙の代表的寸法は次のとおりです。
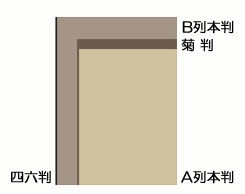
- 1.A列本判 625×880
- 2.B列本判 765×1,085
- 3.四六判 788×1,091
- 4.菊判 636×939